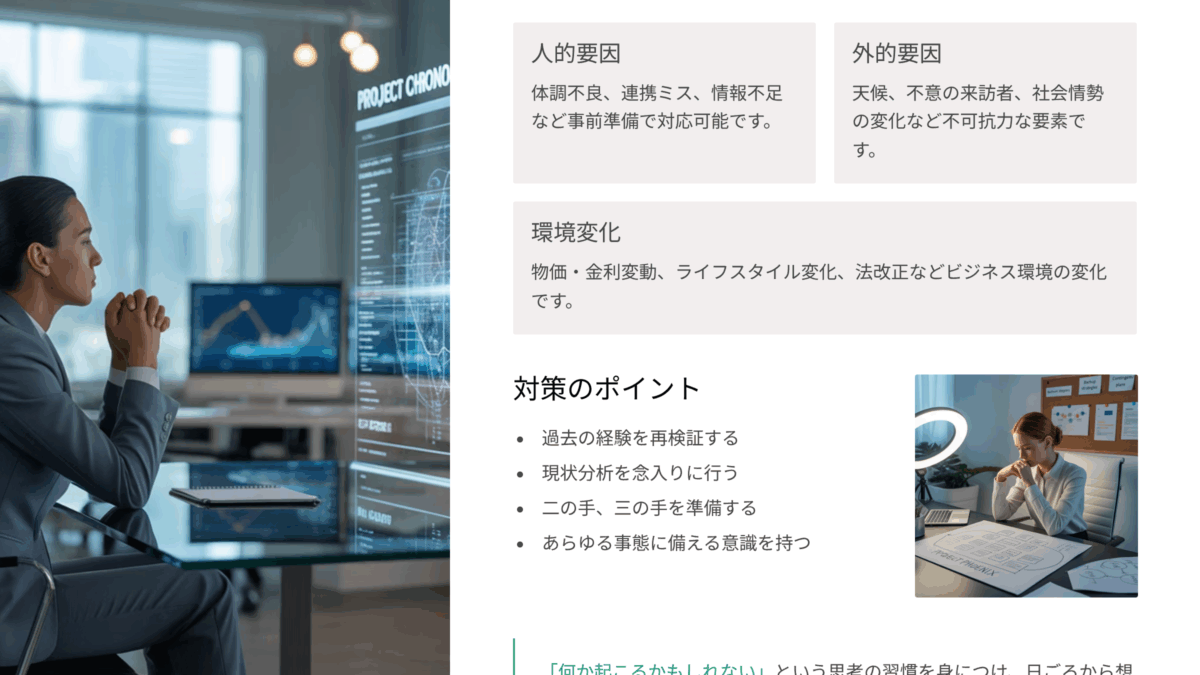9月12日職場の教養 先を読む
予定通りに仕事が進まない、計画通りに運ばないという経験は、誰しもあるでしょう。その要因は、体調不良や連携ミス、情報不足などの人的なものから、天候や不意の来訪者、社会情勢の変化などの不可抗力なものまでさまざまです。人的要因であれば、事前に十分な準備をすることで、予定を崩さずに遂行することが可能です。しかし、外的要因となると、備えるのが難しいこともあります。とはいえ、過去の経験を再検証したり、現状分析を念入りに行なったりすることで、何かが起こる可能性を想定し、二の手、三の手を準備することはできます。昨今は特に、物価や金利の変動、人の動きやライフスタイルの変新、法改正など、ビジネス環境がさまざまな分野で変化しています。そのため、外的要因で予定通りに進まないこともあるでしょう。これらの環境変化を視野に入れ、あらゆる事態に備える意識を持つことが重要です。
「何か起こるかもしれない」という思考の習慣を身につけ、日ごろから想定力を磨くことは、予定や計画を遂行する大きな力になります。
今日の心がけ、想定力を磨きましょう
職場の教養 感想
「先を読む」という言葉を聞くと、未来を予測することだと考えがちです。けれども実際に求められているのは「的中させる力」ではなく、「備える力」ではないでしょうか。
天気予報は外れることもあります。しかし、雨具を用意していれば慌てる必要はありません。同じように、ビジネスの現場でも「こうなるかもしれない」という想定を重ね、二の手三の手を準備しておけば、不測の事態も学びの機会に変わります。
倫理法人会の活動方針には「運営の前倒し化・準備の徹底」という言葉があります。これはまさに“先を読む”ことの実践です。未来を読むこと自体は不確かでも、「準備を重ねた者だけが、いざというときに動ける」という確かさがあるのです。
「万人幸福の栞」にある「気づいた時すぐする」も、準備の延長線にあります。準備を怠らず、気づいたことをその場で処理していく。これが結果的に“先を読む人”をつくるのだと思います。
つまり「先を読む」とは、未来を見通す才能ではなく、日々の準備と想定力の積み重ねそのもの。未来は予測するものではなく、準備によって迎えるものなのです。
ひとり朝礼に対する気分
ひとり朝礼を開始して3日目。やらないといけないからやるという感覚。