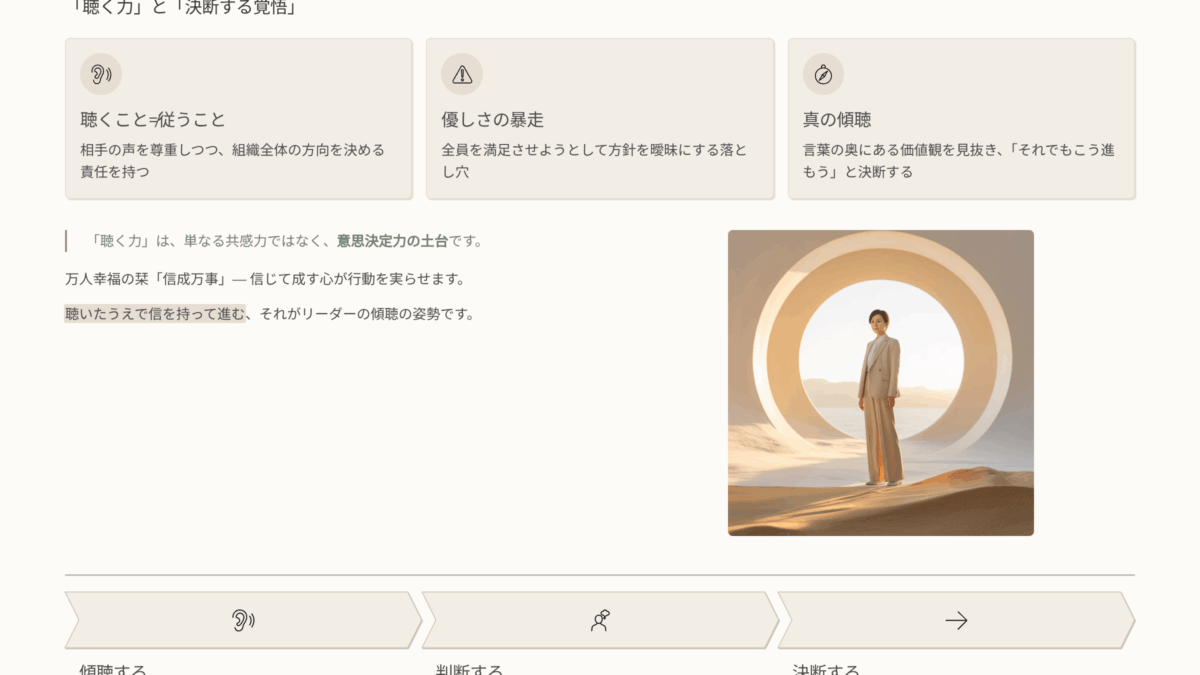職場の教養10/12(日)聴く力
人間関係や信頼関係を築くうえで、どのようにコミュニケーションをとるかは非常に重要です。そこで求められるのが、「聴く力」です。
「聴く」という言葉には、注意深く、あるいは積極的に耳を傾けるという意味があります。相手と会話をする時には、こうした聴く姿勢が欠かせません。
私たちは様々な場面で人と会話をします。時には、互いに悩みを打ち明け合うこともあるでしょう。そんな時は、相手の話を最後までしっかり聴くことが大切です。途中で話を遮ったり、考えを否定したりするのは避けたいところです。ん
また、相手に共感する姿勢を持つことも重要です。つい自分の意見を言いたくなることもありますが、まずは相手の気持ちに寄り添い、受け入れることで、相手も安心して話すことができるのではないでしょうか。
さらに、何か作業をしている時でも、一度手を止めて相手と向き合う、適度に相槌を打つなど、聴く姿勢を整えるための工夫はたくさんあります。
こうした工夫を日常に取り入れることで、傾聴力を身につけたいものです。
今日の心がけ 傾聴力を向上させましょう
職場の教養感想
「聴く力」は、信頼を築くうえで不可欠な資質です。しかし、聴くことと従うことを混同すると、組織は方向を失います。今日のテーマは、リーダーが持つべき“傾聴の境界線”。優しさと決断力をどう両立させるかを考えます。
本文では、人間関係や信頼関係を築くうえで「聴く力」が重要だと述べられています。聴くとは、相手の話を注意深く、積極的に耳を傾ける姿勢のことです。会話の際には、話を途中で遮らず、相手の気持ちに共感し、受け入れることが大切とされています。また、作業中でも一度手を止めて相手と向き合うなど、聴く姿勢を整える工夫が紹介されています。これらを実践することで、傾聴力が高まり、人との関係性がより深まると結ばれています。
リーダーシップの本質は「聴くこと」にあるとよく言われますが、私はそこに一つの落とし穴を感じます。聴くことは受け入れることではあっても、必ずしも「従うこと」ではありません。相手の声を尊重しつつ、組織全体の方向を決める責任はリーダーにあります。
時に、部下の不満や不安を真摯に聴くあまり、全員を満足させようとして方針を曖昧にしてしまうことがあります。それは“優しさの暴走”です。真の傾聴とは、相手の言葉の奥にある価値観や課題を見抜き、必要ならば「それでもこう進もう」と決断する覚悟を含むものです。
「聴く力」は、単なる共感力ではなく、意思決定力の土台です。万人幸福の栞の「信成万事」にあるように、信じて成す心が行動を実らせます。聴いたうえで信を持って進む――それがリーダーの傾聴の姿勢だと感じます。
印象に残った一文
「まずは相手の気持ちに寄り添い、受け入れることで、相手も安心して話すことができるのではないでしょうか。」
→ 聴くことは“同意”ではなく“安心を生む理解”だと再確認できる言葉です。
まとめ
優しさの先に、決断という聴く力を。