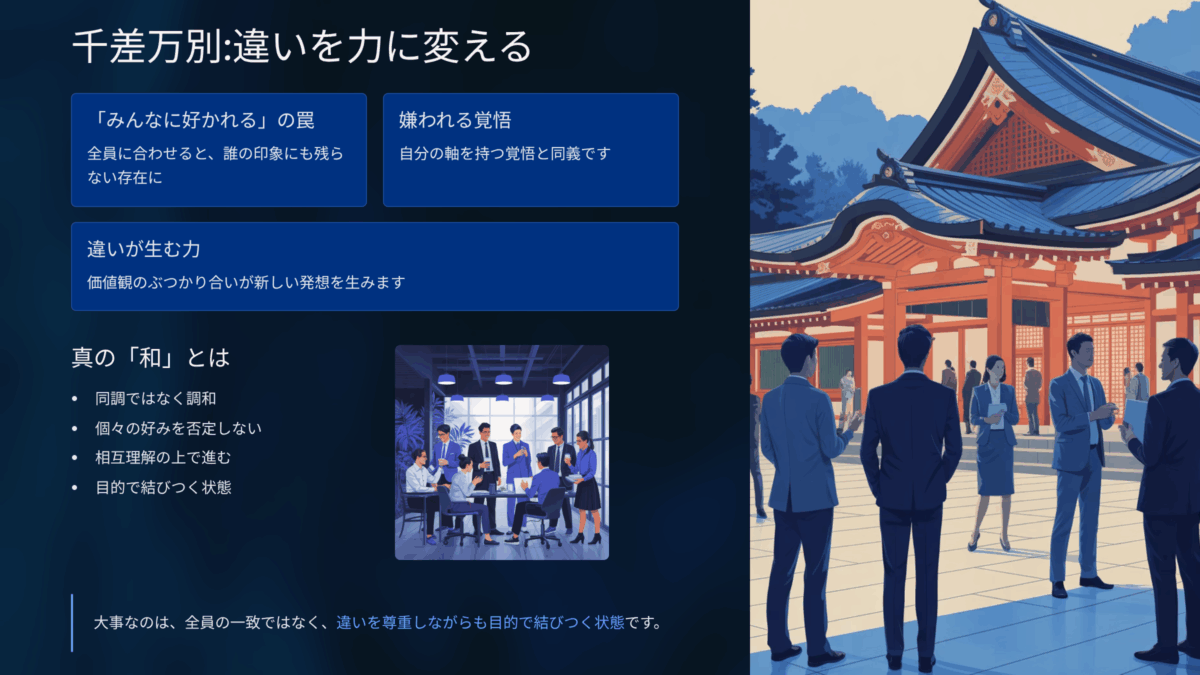職場の教養10月10日
「蓼食う虫も好き好き」という諺があります。
多くの虫にとって苦手とされる、独特の辛味を持つ蓼という植物がありますが、その蓼を好んで食べる虫も存在します。この諺は虫ですら食べ物の好みがあるように、人の好き嫌いも千差万別であるという意味で使われます。
ことわざ自体を聞いたことがあり、意味も知っているという人は多いでしょう。しかし、実際に蓼という植物を見たことがある人はどれだけいるでしょうか。
蓼とは、タデ科植物のヤナギタデ類のことを指します。誰もがイメージできるのが、お刺身のつまによく出る、赤紫の小さい双葉になっている植物です。う
そして、「蓼食う虫」とされるのは、ハムシと呼ばれる体長四ミリ程度の甲虫です。幼虫時だけでなく成虫になってもヤナギタデを食べ続けるそうです。
もし、誰もが同じものを好んだら、枯渇して供給が追い付かなくなるでしょう。多種多様な人がいることで社会は回っています。ビジネスもチャンスは様々なところにあります。訪れた好機を逃さないようにしたいものです。
今日の心がけ 様々なところに着目しましょう
職場の教養 感想
「蓼食う虫も好き好き」は、多様な価値観の象徴です。しかし職場では、つい“みんなに好かれたい”という意識が働きがちです。この記事では、均質化の落とし穴と、多様性を力に変えるための視点を考えます。
本文は「蓼食う虫も好き好き」という諺を通じ、人の好みや価値観がいかに多様であるかを説いています。蓼とはヤナギタデの一種で、一般には辛味が強く食べにくい植物ですが、それを好んで食べる虫(ハムシ)も存在します。この事実から、「もし全員が同じものを好めば、資源は枯渇してしまう」とし、異なる好みや考え方があることで社会が成り立っていると結びます。最後に、ビジネスの世界でも多様な視点に目を向けることが新たな機会を生むと説いています。
感想・学び
職場ではしばしば「みんなに好かれる人」が理想像として語られます。しかし、全員の好みに合わせて動くことは、結果的に誰にも印象に残らない存在になる危険があります。人の好みが千差万別であるなら、「誰かに嫌われる覚悟」は「自分の軸を持つ覚悟」と同義です。
特にチーム運営では、異なる価値観のぶつかり合いが新しい発想を生みます。“みんなが好き”を目指すリーダーは、無意識のうちにチームを無味無臭にしてしまうのです。大事なのは、全員の一致ではなく、違いを尊重しながらも目的で結びつく状態。
万人幸福の栞「和を尊ぶ」も、同調ではなく調和を意味します。個々の好みや意見を否定せず、相互理解の上で進む――その姿勢が、真の「和」をつくるのだと思います。
印象に残った一文(引用)
「もし、誰もが同じものを好んだら、枯渇して供給が追い付かなくなるでしょう。」
――好みの違いは、社会を回す“分散装置”だと気づかされます。
違いを恐れず、調和の中に個性を立たせよう。