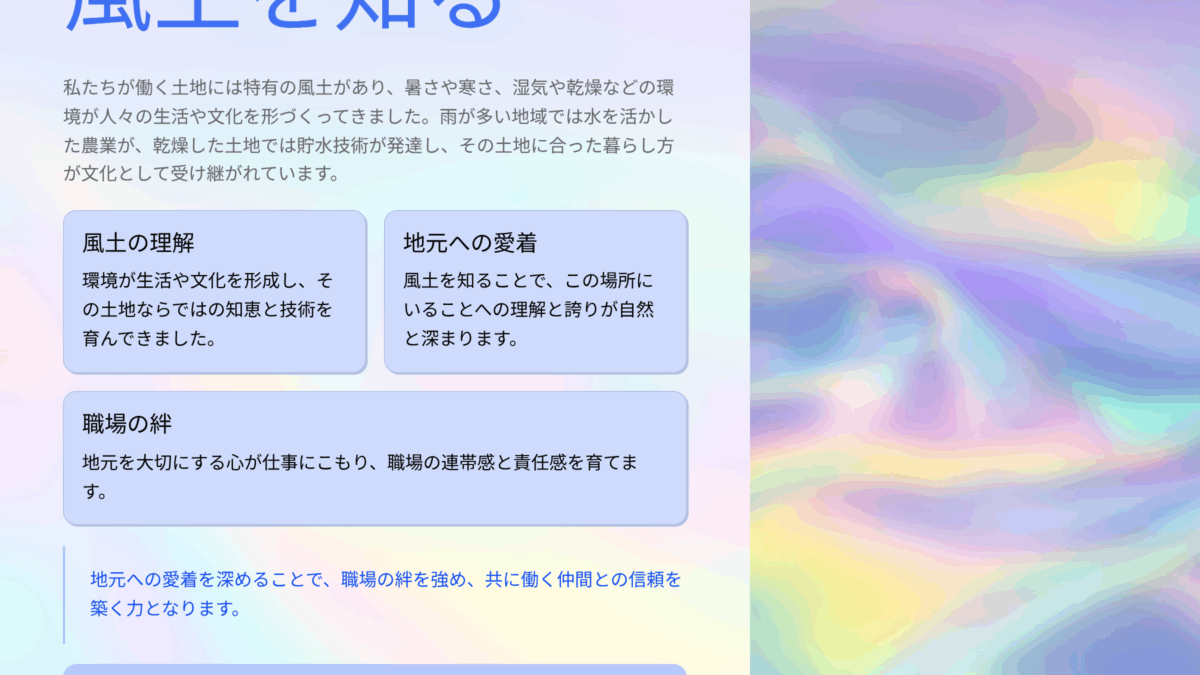9/22(月)風土を知る
私たちが働く土地には、それぞれ特有の風土があります。暑さや寒さ、湿気や乾燥、風の強さ、海や山の近さなど、こうした環境の一つひとつが、そこに暮らす人々の生活や文化を形づくってきました。
例えば、雨が多い地域では、水の恵みを活かした農業が盛んになり、乾燥した土地では貯水の技術が発展してきました。 その土地に合った暮らし方の工夫がなされ、やがてそれが文化や習慣となって今日に受け継がれてきたのです。
こうした風土を知り、その中で働くことの意味を考えると、自分がこの場所にいることへの理解と誇りが自然と深まるでしょう。
地元を知り、風土を尊重することは、単なる郷土愛にとどまらず、より一層この土地や職場を良くしていきたいという思いを高めます。地元への愛着を持ちながら働くことは、職場の連帯感や責任感を育てる大切な土台となるでしょう。
私たち一人ひとりが地元を大切にすることで、仕事にも心がこもります。地元への愛着が、職場の絆を強め、共に働く仲間との信頼を築く力となるのです。
今日の心がけ 地元への愛着を深めましょう
職場の教養 感想
働く土地の気候や地形といった風土が、人々の暮らしや文化を形づくってきた事実を示す。雨量や乾燥など環境に応じた工夫が受け継がれ、今日の慣習につながっていると説明する。さらに、風土を知ることで地域への理解と誇りが深まり、職場を良くしたい気持ちが高まると述べる。地元への愛着は連帯感や責任感の土台となり、仲間との信頼を育む力になると結ぶ。そして「地元への愛着を深めよう」と日々の心がけを促している。
私は郷土愛を“推進剤”として評価しつつも、過剰になると視野を狭めるリスクを感じます。良かれと思う「地元の常識」が、外部の人や新しいやり方をはねのけ、改善機会を失わせるのです。対策は、愛着の「対象」を土地単体でなく“この土地で働く全員の幸福”へ拡張すること。基準が人に移ると、外から来た知恵も守るべき資産になります。また、「標準化」と「土着化」を対立させず、条件を明示して両立させる発想が要ります。例えば“気候要因で変える項目/変えない項目”を最初に宣言する。倫理の実践(明朗・愛和・喜働)で言えば、明朗は前提条件の開示、愛和はよそ者を迎える作法、喜働は地域資源と他所の知を掛け合わせる創造です。
印象に残った一文
「地元を知り、風土を尊重することは、単なる郷土愛にとどまらず、より一層この土地や職場を良くしていきたいという思いを高めます。」
— 愛着が行動のエネルギーに変わる核心を突いているため。