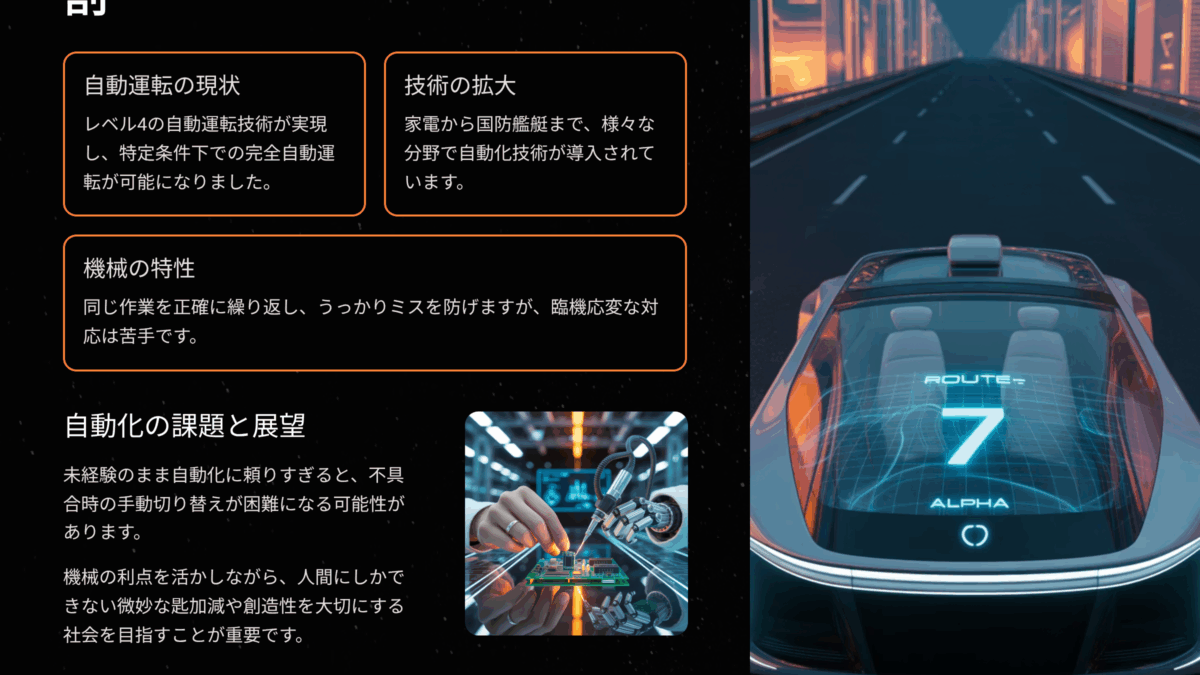9/14(日)自動化との共存
ここ数年、自動車の自動運転技術は急速に進歩しています。
現在、特定の条件下で自動運転が可能なレベル4の段階に達しており、安全性の向上とサービスの普及が進められています。
このような自動化技術は自動車だけにとどまらず、さまざまな分野に広がっています。これまで人間の能力に頼っていた作業を自動化する動きも加速しており、洗濯機などの家電から国防に関わる艦艇まで、多岐にわたります。
機械による自動化は、同じ作業と同じ結果を繰り返し実行できるため、 人間が行なう際に発生する「うっかりミス」を防ぐことができます。しかし、同じ結果しか出せないため、微妙な匙加減や臨機応変な対応は苦手です。
また、未経験や経験不足のまま自動化に頼りすぎると、不具合が発生した際に手動に切り替えることが困難になる可能性があります。
自動化がもたらす利点とともに、その課題にも目を向け、機械にはない人間の力を十分に発揮できる社会を目指すことが重要なのです。
今日の心がけ、機械の役割を見直しましょう
職場の教養感想 自動化社会における「ミスの価値」
自動運転をはじめとする自動化技術は、私たちの生活を安全で便利にしてくれます。とりわけ「人間のミスを防ぐ」ことは、技術の大きな目的の一つでしょう。しかし、ここで立ち止まって考えたいのは、「ミスは本当に無駄なものなのか」ということです。
ミスは確かに不注意や経験不足を映し出し、人間の不完全さを示します。しかしその一方で、ミスは気づきや学びを生み出す大切な契機でもあります。経営の現場でも、思い通りにいかなかった失敗から改善策が見えたり、逆に新しい発想が芽生えることが少なくありません。社員の小さなミスが、業務フロー全体の見直しにつながり、結果として会社全体の成長を促すことすらあるのです。
もし全ての判断を機械が肩代わりし、常に「正しい答え」だけが返ってくる社会になったら、私たちは失敗から学ぶ機会を失ってしまいます。それは一見効率的に見えて、実は人間の力を弱める危うさを孕んでいます。
倫理法人会の栞にある「今日は最良の一日、今は無二の好機」という言葉を思い出します。間違えたり、つまずいたりする「今」もまた、かけがえのない成長の機会です。自動化の恩恵を受けつつも、人間ならではの「不完全さ」を見直すとき、私たちはより豊かな未来を創り出せるのではないでしょうか。