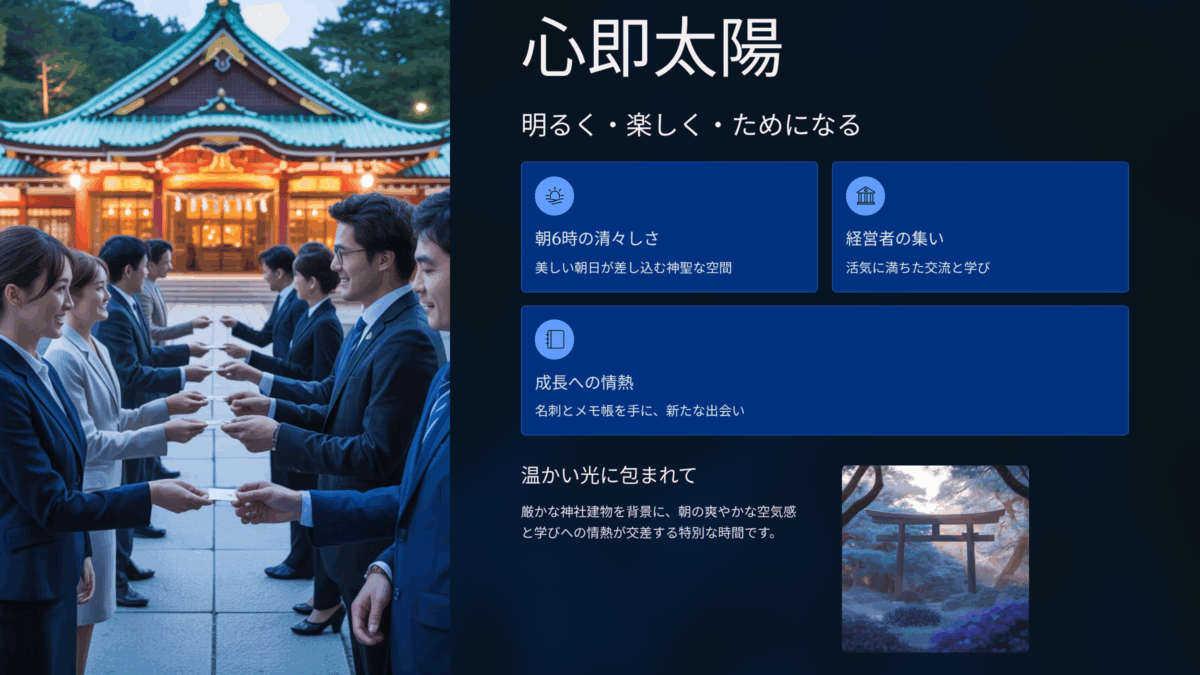「普通じゃないから、普通になりなさい」と言われ続けてきた青年が、「普通にならない」ことを選んだ――。
倫理法人会の講話で語られた深田和裕さんの生き方には、自己受容と多様性を尊ぶ“新しい倫理”が息づいています。
「普通にならない」と決めた瞬間
深田和裕さんは、学生時代に「普通じゃない」と言われ続けてきたという。
社会はしばしば“平均”を安心の基準とし、そこから外れる存在を異端視する。だが彼はその圧力に抗うのではなく、自然体で受け入れて生きてきた。
彼の人生は、まさに“多様性”の実践そのもの。
電気工事業、農業、IT、デザイン――十二の職を経験し、「何でもできる、何でもなれる」という信念のもとに挑戦を続けてきた。
職を転々とすることは、彼にとって「逃げ」ではなく「自由」だった。
「同じ仕事にこだわらん方がいい。いろんなことをやるうちに、世の中の仕組みが見えてくる。」
その姿勢こそ、『万人幸福の栞』第四条「人は鏡、万象はわが師」の実践である。
自分を受け入れるという強さ
深田さんは自らの特性「2E(twice exceptional)」を率直に語った。
発達的な凹凸を持ちながらも突出した才能を発揮するタイプで、人口の0.4%といわれる希少な存在だという。
彼はその特性を「欠陥」ではなく「個性」として受け入れ、同じような人たちが安心して集える場をつくろうと動いている。
社会が求める「普通」ではなく、「自分らしさ」を基準に生きる。そこには「まず自らを改めることで相手も変わる」という倫理実践の精神がある。
離れていても“親を大切にする”
深田さんの語りで特に印象的だったのは、実の両親と20年以上絶縁しているという話だった。
「親を大切にする」という倫理の基本を真っ向から問う内容だが、彼の考え方は独自だ。
「関わらないことが、いまの自分にとっての“親を大切にする”なんです。」
感謝を持って距離を取る。墓参りを欠かさず、衝突しないことで平和を保つ。
その姿はまさに「愛和」の新しい形。愛とは、同じであることを強いることではなく、違いを認め合うことだと教えてくれる。
「ハッシュ」に込めた未来への祈り
現在、深田さんは「ハッシュ(Hush)」という屋号で事業を営む。
これは「播種(種まき)」と「寄せ集める」という二つの意味を掛け合わせたもの。
「小さな力を集めて未来に種をまく」という理念のもと、電気工事、農業、コンサル、教育など幅広く活動している。
この考え方は、『栞』第八条「明朗は健康の父、愛和は幸福の母」にも通じる。
多様な人が自分の個性を生かして働ける社会は、必ず明るく、健康になるのだ。
自己受容から始まる“利他”の倫理
深田さんの生き方の根底にあるのは“自己受容”である。
できないことを責めず、できることを伸ばす。
「100年後の公園で笑うのは、僕でなくてもいい。」
この言葉は、彼の人生哲学を象徴している。成果を次の世代に託し、未来の笑顔のために働く。
それはまさに「信成万事」の生き方であり、倫理経営の真髄だ。
結びに代えて:普通を超えて、真の自分へ
“普通にならない”という選択は、反抗ではなく調和の始まりだ。
平均に合わせるのではなく、自分のまま他者と響き合う。
それこそ「万象我師」の実践であり、これからの時代に求められる倫理観である。
違いは壁ではなく、学びの入口。
「普通でない」という言葉は、欠点ではなく可能性の別名。
そして、自分の鏡に映る他者を素直に見つめるとき、
私たちはようやく“自分自身を生きる”ことができるのだ。
🌸 今日の気づき
「普通でなくてもいい」――それは自分を信じる第一歩。
自分を受け入れ、他者を認める。そこから真の調和が始まる。
まとめ
多様性を恐れず、自分を受け入れて生きる。
それが、倫理の心を実践する第一歩です。