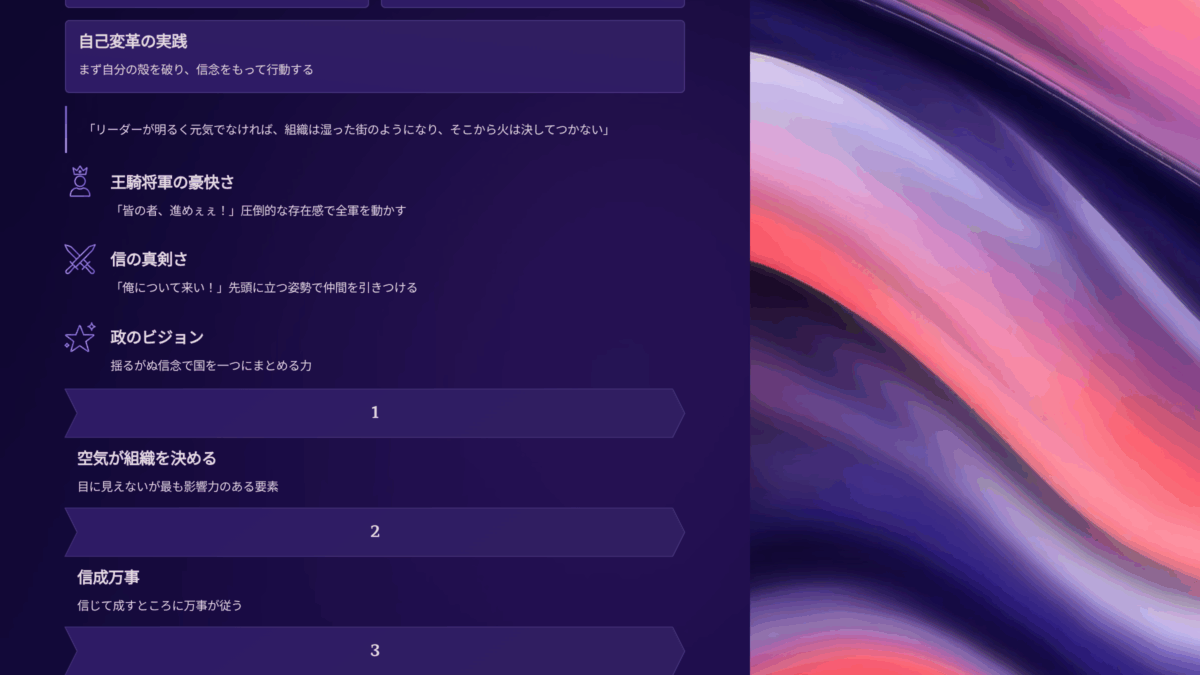先日の華房会長の講話の中で、私の心に強く響いた言葉がある。それは「リーダーの仕事は組織の空気づくりだ」という一言であった。会長は「リーダーが明るく元気でなければ、組織は湿った街のようになり、そこから火は決してつかない」と語られた。さらに、「おはようございます!」と力強い挨拶を繰り返すことの意味を説かれたが、その言葉は単なる掛け声ではなく、リーダーが演出者であり役者であるという覚悟を物語っていた。私はその姿勢に深く感銘を受けると同時に、組織運営における「空気」の重要性を改めて考えるきっかけをいただいた。
空気が組織を決める
考えてみれば、組織において「空気」は目に見えないが、最も影響力のある要素の一つである。社員が安心して挑戦できるかどうか、仲間同士が互いに信頼し合えるかどうか、そしてその場にいるだけでやる気が湧くかどうか。これらはすべて空気によって左右される。どんなに優れた戦略や仕組みを整えても、空気が澱んでいれば機能しない。逆に、空気が明るく前向きであれば、多少の不備があっても組織は自ずと前進していく。
実際、経営現場では「数字ばかりを追い求めるあまり職場の空気が重苦しくなり、会議で発言が減った」という話をよく耳にする。そこで気づかされるのは、社員を変えようとする前に、自らの姿勢を変えなければならないということだ。「最近、社長が笑わなくなった」と社員から指摘されて、初めて自分が組織を淀ませていたことに気づく経営者も少なくない。つまり、組織の空気はトップの姿勢を映す鏡である。
『キングダム』に見る空気の力
この「空気づくり」という視点を、漫画『キングダム』の場面から考えるとさらにわかりやすい。戦場において兵士たちの士気を決めるのは、戦術や武器だけではない。リーダーが放つ空気そのものだ。
王騎将軍はその象徴である。彼が豪快な笑顔で「皆の者、進めぇぇ!」と叫ぶとき、兵士の恐怖心は一瞬にして吹き飛び、全軍が生き生きと動き出す。あの圧倒的な存在感と明るさが、戦場全体を突き動かす力になっていた。
また、飛信隊の信も、自らが誰よりも先頭に立ち「俺について来い!」と叫ぶことで仲間を引きつけていった。未熟さを抱えながらも、真剣さと必死さが仲間の心を動かし、隊の空気を変えていったのだ。そして政(後の始皇帝)は、揺るがぬ信念と未来へのビジョンを語り続けることで、国を一つにまとめていった。人々はその空気に惹かれ、共に国づくりに挑んだ。
これらの場面は、戦場に限らず企業や地域社会にそのまま通じる。リーダーの姿勢が空気を決め、その空気が組織の命運を左右するのである。
リーダーは演出者であり役者
華房会長は「リーダーは演出者であり役者である」と語られた。これは決して自分を偽ることを意味しない。むしろ、感情や都合に流されず、組織のために望ましい姿を体現することを意味する。リーダーが「明朗・愛和・喜働」を演じることで、その空気は自然と組織全体に波及していく。倫理法人会が唱える「明朗は健康の父、愛和は幸福の母」という教えも、この姿勢と重なるだろう。
経営者が明るく元気であることは、単なる気分の問題ではない。戦略や数字と同等、いやそれ以上に大切な経営の基盤である。
自己変革が空気を変える
さらに華房会長は「倫理は自己変革である」と繰り返された。役職を引き受けることや、実践を積み重ねることは、すべて自分を変えるための挑戦だという。リーダーが空気を変えるには、まず自分の殻を破る必要がある。
「信成万事」という言葉がある。信じて成すところに万事が従う、という意味だ。リーダーがまず自分を信じ、理想の姿を信じて演じ切ることで、初めて周囲は変わり始める。組織の空気は自然には変わらない。トップが信念をもって行動し、明るく元気に演じ切ることでようやく変わっていく。信じて演じることが空気をつくり、その空気が組織を未来へと導いていくのだ。
空気の職人として
改めて考えると、私たち経営者やリーダーは「空気の職人」である。日々の挨拶、表情、言葉、姿勢。その一つひとつが空気をつくり、社員や仲間の心に作用する。空気は目に見えないが、確かに存在し、人を動かす力を持っている。
華房会長の講話と『キングダム』の物語を重ね合わせると、リーダーの役割は未来を描くことや戦略を練ること以上に、「空気をつくること」にあると確信できる。明るく元気に、誠実に、そして楽しげに。そんな空気をまとったリーダーのもとでこそ、組織は力を発揮し、社員は幸せを感じる。
これからも私たちは「空気の職人」として、自らを磨き、明るい空気を演じ続けたい。その空気が社員の喜びと成長を生み、やがて社会全体に広がっていくことを願ってやまない。